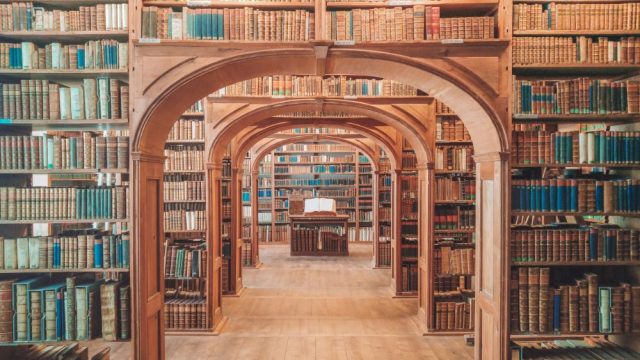国家総合職は、政策の企画・立案など国の中枢に関わる業務を担う、いわゆるキャリア官僚として活躍できる職種です。専門知識やスキルを活かして国に貢献できることから、「将来は専門分野の知識を活かして活躍したい」と考えている方にとって理想的なキャリアパスの一つといえるでしょう。
本記事では、国家総合職の概要や、国家一般職との違い、院卒者試験の内容についてわかりやすく解説します。院卒者試験の合格率やスケジュール、国家総合職を目指す際のポイントも紹介するため、ぜひ参考にしてください。
国家総合職とは
国家総合職は、政策の企画や立案、法案の作成など、高度な知識・技術・経験を要する業務に従事する国家公務員です。主に各省庁の中央官庁で、国の将来を見据えた政策づくりに携わるゼネラリストとして活躍します。
国内にとどまらず世界規模の課題に取り組むこともあるため、グローバルな視野を持ち、社会の変化に敏感に対応できる人に向いている職種です。
国家総合職と国家一般職の違い
政策の企画・立案等を行う国家総合職に対して、国家一般職は、各府省の出先機関などの現場において、国家総合職が企画・立案した政策の実施・運用や、事務業務などを行う職種です。基本的に、特定の分野の専門家として、一つの部署で長く経験を積みます。
また、国家総合職には院卒者試験が設けられており、このことから、国家総合職の採用において、院卒者には大卒者とは異なる知識・技能を求めていることがわかります。これは、専門性の高い知識・技能を備えた院卒者としての活躍が期待されているといえるでしょう。
【国家総合職と国家一般職の違い】
| 国家総合職 | 国家一般職 | |
| 仕事内容 | 政策の企画・立案、他省庁との調整・連携など幅広く行う | 政策の実施・運用など、定型的な事務業務が中心 |
| 給与 |
|
|
| 試験の難易度 | 出題範囲が広く、専門記述試験や政策論文試験などが課される。官庁訪問により内定が決まるため、二次試験合格後も競争が続く | 出題範囲は国家総合職に比べると狭く、専門記述式試験は少ない。二次試験合格で採用まで進む |
※本府省に採用された際の初任給の目安
以下では、国家総合職と国家一般職の主な違いについて詳しく説明します。
仕事内容
国家総合職は、将来の幹部候補生として、政策の企画・立案や法案の作成、他省庁との調整・連携など、幅広い業務を担当します。
一方、国家一般職は、事務作業などの定型的な業務を中心に担当します。中央省庁においては国家総合職とともに政策の立案・企画をする機会もありますが、政策を実際に運用し、企画・立案を支えることが基本です。
年収
国家総合職は、国家一般職と比べて年収が高い傾向があります。総合職は将来的に重要な役職に就くことが多く、業務の責任が大きいためです。
人事院の公式サイトでは、本府省に採用された際の初任給の目安が次のように示されています。
【総合職試験採用者】
【一般職試験採用者】
|
なお、国家一般職には、院卒者試験はありません。上記の初任給を比較すると、同じ大卒程度試験であっても、国家総合職のほうが高い給与水準であることがわかります。
試験の難易度
国家総合職の試験は、国家一般職に比べて出題範囲が広く、難易度が高い傾向にあります。特に二次試験では、専門記述試験や政策論文試験などが課され、より高度な知識と論理的思考力が求められます。
さらに、二次試験に合格しても、それだけで採用が決まるわけではありません。国家総合職として働くためには、合格後に行われる官庁訪問で内定を得る必要がありますが、どこからも声がかからないケースもあります。
国家総合職の試験区分
国家総合職の試験区分は、以下の10区分に分類されています。それぞれの区分は、専攻分野に合わせて選択できます。
| 試験区分 | 概要 |
| 行政 | 法学や経済学、政治学などを専攻する学生向けの区分。憲法や行政法、民法などの法律科目が出題される。受験者が多く、一般的な文系学生に適している |
| 人間科学 | 心理学や教育学、社会学などを専攻する学生向けの区分。2024年度に新設された |
| デジタル | 情報工学などを専攻する学生向けの区分。基礎数学や情報基礎、情報技術などの知識が問われる |
| 工学 | 機械や電気、土木、建築などの工学系を専攻する学生向けの区分。数学や物理、工学などの知識が問われる |
| 数理科学・物理・地球科学 | 数学や物理学、地球科学などを専攻する学生向けの区分。基礎数学や解析、確率統計、物理学、地球科学などの知識が問われる |
| 化学・生物・薬学 | 化学や生物学、分子生物学などを専攻する学生向けの区分。物理化学や無機化学、有機化学、生化学、分子生物学などの知識が問われる |
| 農業科学・水産 | 生物資源科学や食料事情、統計学などを専攻する学生向けの区分。作物学や園芸学、育種遺伝学などに関する知識が問われる |
| 農業・農村工学 | 農業や農業工学を専攻する学生向けの区分 |
| 森林・自然環境 | 森林科学、環境科学などを専攻する学生向けの区分。森林関連以外にも、生物や地学の知識も問われる |
| 法務 | 司法試験合格者のみが受験できる区分。法律の専門知識を活かして行政に携わることを志望する学生向け |
なお、国家総合職には教養や法律、経済、政治・国際・人文という区分もありますが、大卒に限定されています。
国家総合職の院卒者試験の内容
国家総合職の院卒者試験は、第1次試験、第2次試験、官庁訪問という流れで実施されます。
第1次試験
国家総合職の院卒者試験の第1次試験は、基礎能力試験と多肢選択式の専門試験から構成されています。
基礎能力試験は、すべての区分で共通して実施される試験です。問題は、文章理解や数的処理といった一般知能分野に加えて、自然・人文・社会に関する時事、情報といった一般知識分野から出題されます。
一方、多肢選択式の専門試験は、選択した区分によって出題内容が異なります。たとえば、行政区分の場合、受験者は出題内容の異なる3つの選択群の中から1つを選ぶ形式となっており、選択Ⅰは政治・国際・人文系科目、選択Ⅱは法律系科目、選択Ⅲは経済系科目が中心です。それぞれの選択群には、必ず解答する必要のある科目と、受験者が選択して解答する科目が含まれています。
第2次試験
国家総合職の院卒者試験の第2次試験は、記述式の専門試験と政策課題討議試験、人物試験から構成されています。
記述式の専門試験では、選択した試験区分に応じた専門科目から2題が出題され、記述式で回答します。内容は選択式で出題される専門試験と重なる部分もあり、各科目の理解を深めておくことに加えて、記述形式に慣れるための答案練習も欠かせません。
政策課題討議試験では、与えられたテーマに対して、他の受験者とグループで議論しながら結論を導き出す力が試されます。最初に意見をまとめたレジュメを作成した後、個別発表を経て、グループ討議に進むという流れです。
人物試験では、人事院の面接官3名による個別面接が行われます。質問は事前に提出した面接カードの内容に沿って進められ、受験者の考え方や行動の特徴を掘り下げて評価する「コンピテンシー評価型」の面接形式が採用されています。
参考:2025年度 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)受験案内 |人事院
官庁訪問
国家総合職試験は、最終合格が出ても内定が得られるわけではありません。最終合格発表後に採用を希望する各府省庁を訪問して選考を受ける官庁訪問を経て、採用内々定を得る必要があります。
面接内容は省庁により異なりますが、基本的には人事課面接や原課面接が行われます。人事課面接は志望動機や自己PRなど、原課面接では実際にその部署で働いている職員との対話を通じて適性を見る面接です。
国家総合職の院卒者試験の受験資格
国家総合職の院卒者試験を受験するためには、年齢と学歴の条件を満たしている必要があります。年齢については、30歳未満であることが求められ、学歴に関しては修士以上の学位をすでに取得しているか、試験実施年度の修了見込みであることが必要です。
以下では、2025年度に実施される国家総合職試験の受験資格を紹介します。
| 【法務区分を除く区分の場合】
1995年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
【法務区分の場合】 1995年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
|
国家総合職における大学院卒者の合格率
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)実施状況 2024年度によると、各試験区分の受験者数、第1次試験合格率、最終合格率は以下のとおりです。
| 試験区分 | 受験者数 | 第1次試験の合格率 | 最終合格率 |
| 行政 | 235人 | 90.6%(213人) | 71.5%(168人) |
| 人間科学 | 84人 | 94.0%(79人) | 72.6%(61人) |
| デジタル | 46人 | 100.0%(46人) | 56.5%(26人) |
| 工学 | 212人 | 85.8%(182人) | 59.9%(127人) |
| 数理科学・物理・地球科学 | 106人 | 98.1%(104人) | 54.7%(58人) |
| 化学・生物・薬学 | 274人 | 89.7%(156人) | 32.1%(88人) |
| 農業科学・水産 | 104人 | 92.3%(96人) | 65.4%(68人) |
| 農業農村工学 | 13人 | 84.6%(11人) | 69.2%(9人) |
| 森林・自然環境 | 72人 | 97.2%(70人) | 73.6%(53人) |
| 法務 | 11人 | 100.0%(11人) | 90.9%(10人) |
| 合計 | 1,057人 | 91.6%(968人) | 63.2%(668人) |
参考:国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)実施状況 2024年度
合格率に注目すると、最も高かったのは「法務」の90.9%です。次いで「森林・自然環境」が73.6%、「人間科学」が72.6%、「行政」が71.5%と続きます。一方、合格率が最も低かったのは「化学・生物・薬学」の32.1%で、特に競争が激しい区分であることがうかがえます。
全体の最終合格率は63.2%であり、これは約1.6倍の倍率を意味します。つまり、受験者のうち約3人に2人が最終合格している計算です。国家総合職は高い専門性が求められる試験であるものの、計画的に対策を進めれば、十分に合格を狙えることがわかるでしょう。
国家総合職の院卒者試験のスケジュール
国家総合職の院卒者試験の年間スケジュールを把握しておくことは、効率的な対策を立てるうえで非常に重要です。以下に、例年の実施時期の目安をまとめました。
| 受付期間 | 2月上旬~2月下旬 |
| 第1次試験日 | 3月中旬 |
| 第1次試験の合格発表日 | 3月下旬 |
| 第2次試験:筆記試験 | 4月中旬 |
| 第2次試験:政策課題討議試験・人物試験 | 5月上旬~5月中旬 |
| 最終合格者の発表日 | 5月下旬 |
| 官庁訪問 | 6月上旬から7月上旬 |
具体的な試験日は年度によって異なるため、人事院からの発表を確認してください。
大学院卒者が国家総合職として働くメリット
![]() 大学院で専門的な知識・技能を身につけた人にとって、国家総合職は魅力的なキャリアの選択肢です。冒頭でも説明したように、国家総合職の採用試験には院卒者試験が設けられており、高度な知識・技能を身に付けた人としての活躍の場があるといえます。ここでは、大学院卒者が国家総合職として働く主なメリットを紹介します。
大学院で専門的な知識・技能を身につけた人にとって、国家総合職は魅力的なキャリアの選択肢です。冒頭でも説明したように、国家総合職の採用試験には院卒者試験が設けられており、高度な知識・技能を身に付けた人としての活躍の場があるといえます。ここでは、大学院卒者が国家総合職として働く主なメリットを紹介します。
大学院で培った専門性を活かせる
大学院の研究活動を通じて、専門知識や分析力、問題解決能力などが身につきます。国家総合職は、行政、デジタル、工学、法律など多様な分野に分かれており、自分の専門性をそのまま業務に活かせる場が豊富にあります。
たとえば、工学系を専攻した場合には、インフラ整備に携われます。農学系を修了した場合には、農業政策の立案などで、研究成果を社会に還元できるでしょう。
このように、大学院で積み重ねた専門的な知識やスキルを社会の課題解決に役立てられる点は、大学院卒者にとって大きな魅力といえます。
国に貢献できる仕事に携われる
国家総合職として働く大きな魅力の一つは、国の制度設計や政策立案の最前線で、社会全体に影響を与える仕事に携われることです。大きな責任とともに、社会貢献の実感を得られます。
また、大学院で培った論理的思考力や分析力、専門知識を活かして、社会課題の解決を目指す政策を企画・立案できる点も、大きなやりがいです。大学院で身につけた知見やスキルを、実社会の中で活かしたい、国家や社会に還元したいと考える方にとって、国家総合職は非常に魅力的なキャリアパスといえるでしょう。
国家総合職を目指す際のポイント
先述した通り、国家総合職の試験の難易度は高く、試験に通過するためには綿密な計画が必要です。ここでは、国家総合職を目指すうえで、押さえておくべき重要なポイントについて解説します。
遅くとも1年前から対策を始める
国家総合職試験は出題範囲が広く、深い理解が求められるため、遅くとも試験の1年前から対策を始めましょう。
一般的に、公務員試験の対策に必要な勉強時間は 1,000~1,500時間程度と言われています。たとえば、1日3時間の学習を継続すれば、1年間で約1,100時間の勉強時間を確保することが可能です。
国家総合職では、特に専門科目や記述試験への対策に多くの時間を要するため、計画的な学習が欠かせません。さらに、筆記試験だけでなく、官庁訪問の対策も重要です。筆記と並行して、早い段階から面接対策も進めておきましょう。
過去問を研究して出題傾向を把握する
国家総合職試験の対策として、過去問の研究が有効です。出題傾向や頻出分野を把握できるため、学習の方向性が明確になります。また、自分の苦手分野が可視化されるため、効率的な学習計画を立てやすくなります。
目安としては、過去10年分の問題を解くことがおすすめです。1回解いて終わりにせず、必ず復習し、繰り返し解くことで知識を定着させましょう。さらに、時間を計りながら解く練習を行うと、本番でも落ち着いて回答できます。
過去問は人事院に情報公開請求を行うことで入手できますが、申請から取得までに時間がかかるため、早めの準備が必要です。
まとめ:国家総合職の合格には計画的な準備が不可欠
![]() 国家総合職は、政策の企画や立案など国の中枢業務を担う重要な職種です。行政や人間科学、デジタルなどさまざまな試験区分が設けられているため、自分の専攻分野に合った試験区分に申し込みましょう。
国家総合職は、政策の企画や立案など国の中枢業務を担う重要な職種です。行政や人間科学、デジタルなどさまざまな試験区分が設けられているため、自分の専攻分野に合った試験区分に申し込みましょう。
国家総合職の院卒者試験は、第1次試験、第2次試験、官庁訪問という流れで実施されます。合格のためには、遅くとも1年前から計画的に対策を始め、過去問を研究して出題傾向を把握することが重要です。
「将来は専門分野の知識を活かして活躍したい」と考えている方は、国家総合職として社会に貢献するキャリアを検討してみてはいかがでしょうか。大学院に進学すると研究活動で忙しくなるため、しっかりと学習計画を立てて、合格を目指してください。
中央大学大学院の資料請求はこちら