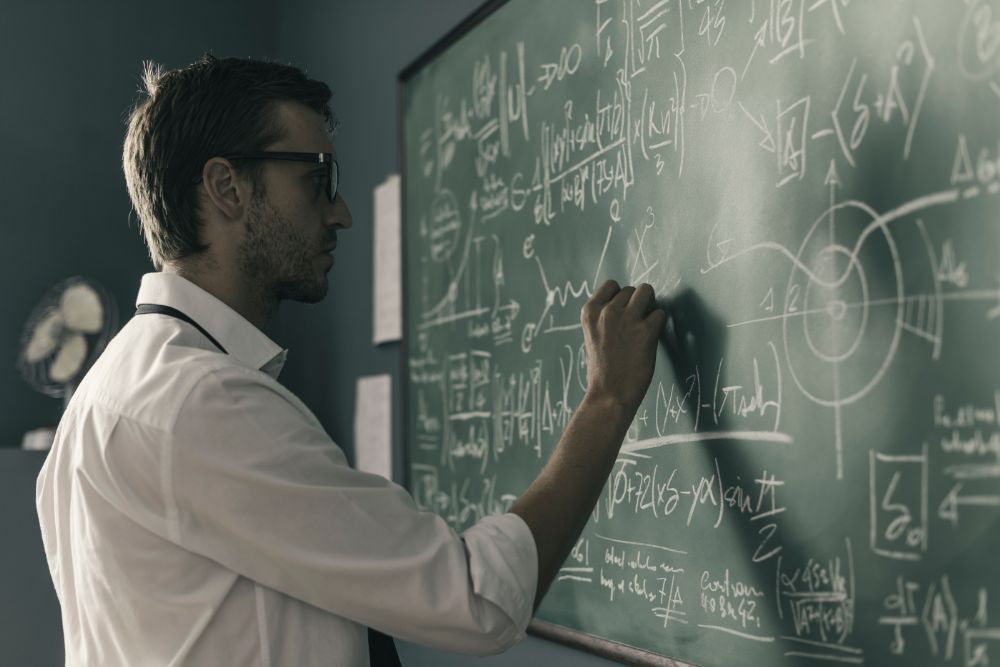大学で学習に励む方々の中には将来の進路として大学教授に興味のある方もいるでしょう。しかし、大学教授になるためにどのようなキャリアを歩む必要があるのか、なかなか知る機会はありません。大学教授になるにはさまざまなプロセスが必要です。この記事では大学教授になる方法を、必要な資質や取り組むべきことと併せて解説します。
大学教授(大学教員)になる方法
大学教員になるための一般的な方法を、3つのプロセスに分けて解説します。
- 修士号・博士号を取得する
- 大学教員として就職活動する
- 大学教員としてキャリアアップする
修士号・博士号を取得する
大学教員になるには、修士号・博士号といった学位の取得が求められる場合が多いです。今日においては、博士号の取得が必要となってきています。研究や学生の指導には高度な専門知識が求められるためです。
修士号・博士号はそれぞれ修士課程(博士前期課程)・博士課程(博士後期課程)を修了すると取得できます。
修士課程は学部を卒業した後に進学する大学院の課程です。専門の研究分野とテーマを選び、教員から指導を受けながら研究を進めます。所定の単位の修得と修士論文審査に合格すると修士号を取得できます。修士課程の修了に必要な期間は2年であることが一般的です。
博士課程は修士課程修了後に進学する課程です。専門分野をさらに深く掘り下げ、自らテーマを選び、より高度な研究を進めます。所定の単位の修得と博士論文審査に合格すると、博士号を取得できます。博士論文の審査は厳しく、専門分野における新しい知見の提供が求められます。
また、大学教員として就職するには、博士論文の執筆の他、一定程度の研究業績を積んでいくことが求められます。
博士課程の修了に必要な期間は通常3年間です。しかし、6年制の学部(医学・歯学・薬学・獣医学部など)の場合は、学部卒業後に直接進学し、4年間在学します。
大学教員として就職活動する
修士号・博士号を取得した後は、大学教員になるための就職活動が必要です。求人を調べて応募し、書類審査を経て面接を受けるというステップで進みます。求人に応募する際には、履歴書に加え、自らの研究実績、論文や学会での発表などの成果をまとめた業績書という書類を送付します。
面接では、これまでの研究や成果、今後の研究計画などについて質問されるので、事前に準備しておきましょう。面接の回答には「その大学だからこそ実現できること」を含めることが大切です。
その他、模擬授業の実施を求められるケースもあります。大学によって採用選考の形式は異なるため、事前に確認しておきましょう。
大学教員の求人は、各大学の公式サイトのほか、研究職を扱うJREC-INなどのサイトに掲載されています。一般的な求人情報サイトには掲載されていないことが多いです。
大学教員としてキャリアアップする
大学教員として就職すると、教授を目指してキャリアアップを重ねます。「博士研究員→助教→講師→准教授」のようなステップを踏み、最終的に教授を目指すのが一般的です。まず、それぞれの役職について解説します。
| 博士研究員
(ポスドク) |
任期付きで大学へ所属する研究者で「ポスドク」とも呼ばれる。研究者としての実績を積み、助教のポストを目指す。任期内に研究結果を出すことが求められる。 |
| 助教 | 自身の決めたテーマの研究に加えて、学生への指導も行う。博士研究員同様任期付きであることが多い。 |
| 講師
(兼任講師、非常勤講師) |
教授または准教授に準ずる職務で、助教と同様に自身の研究と学生の指導の両方に携わる。 |
| 准教授 | 無任期の専任教員であり、准教授は教授の職に準ずる職である。多くは自身の研究室を持っており、研究や学生の指導を行う。 |
博士課程修了後すぐに無任期の専任教員として採用されることは、なかなか難しいです。
そのため、まず任期付きの博士研究員や任期制助教、非常勤講師などを経て教育歴を積み、その間に自身の研究業績を増やしていきます。その後、それらの教歴や研究業績を携え、無任期の大学教員の職を得るという流れを辿ることが多いです。
無任期の大学教員として就職した後は、学生への教育・研究指導とともに、自身の研究活動も行い、助教・准教授から教授を目指すことになります。
大学教員になるためにすべきこと
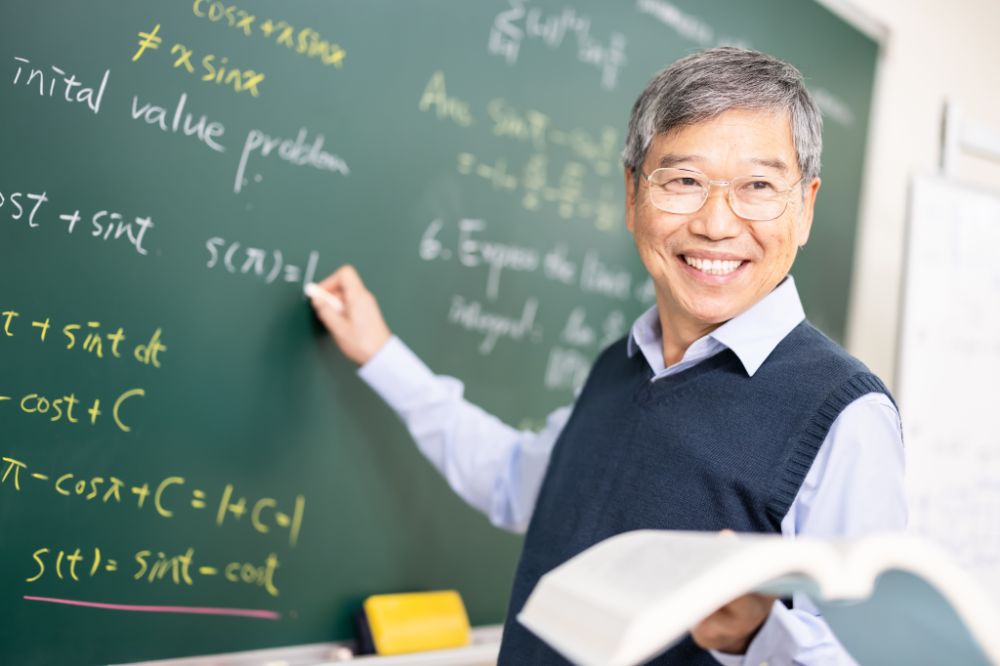 次に、大学教員になるためにすべきことを解説します。
次に、大学教員になるためにすべきことを解説します。
- 大学院に進学する
- 専門分野を決める
- キャリアプランを考える
- 専攻分野の勉強を重ねる
大学院に進学する
まず大学院に進学し、修士・博士の学位取得を目指しましょう。前述した通り、大学で働くには博士号や研究実績が必須要件となることがほとんどです。
大学院や研究科は、自分の興味やキャリアの目標を実現できるかを考えて選びましょう。以下のポイントは研究に大きく関わるため、事前に確認しておきましょう。
- 研究分野
- 研究資金
- 研究設備
- 研究室から発表された論文
- 学会発表の機会
また、修士課程に進学するには入試を受ける必要があります。入試では専門分野と英語などの外国語の合わせて2科目が筆答試験として科されることが多いです。
専門分野の科目の試験は学部レベルの知識を確実に身につけることが重要です。講義や教科書の内容を日頃から復習しておきましょう。また、小論文が出題される場合もあるため、自らの意見について論理的に文章をまとめる練習をしておきましょう。
専門分野を決める
大学教員として研究したい専門分野を決めましょう。大学教員は特定の分野を深く探究することになるため、強い興味を持って長期的に取り組める科目を選びます。
専門分野を決めるには自己の興味と適性を深く掘り下げることが重要です。過去の研究を振り返り、自身がどのような興味や問題意識を持っているかを自覚するのが大事です。加えて、さまざまな研究分野にも触れて、自分がどこに興味を持てるのかを確かめるのもよいでしょう。論文や文献を読んだり、教員訪問を行ったりするのがおすすめです。
また、先行研究を遡るなかで、その分野で解き明かされていないことが何なのかを明らかにしておきましょう。研究者として実績を残していくためには、他の多くの人が取り組んでいない分野を見つけることも重要です。
キャリアプランを考える
専門分野を決めた後は、大学教授になるためのキャリアプランを考えましょう。教授職という長期にわたるキャリアを見据えるには、目標を設定することが望ましいです。
目標には、研究者として成し遂げたい実績や大学教員としてのあり方を据えましょう。例えば薬学系の研究者になりたい場合、世の中に影響を与えるような新薬を開発する、等が目標に該当します。
長期的な目標を考える際には、まず現在から目標までのロードマップを描きましょう。ロードマップを通じて、現在達成すべき目標が明らかになります。例えば、薬学の例では携わる分野の基本的な知識を学部時代に身に着けておくなどが考えられます。
専門分野に関する勉強を重ねる
学部時代から専門分野の勉強をしておくとよいでしょう。
例えば、最新の研究論文を読み、それらについて自分なりの批評や考察を加えることは、批判的思考能力を養う上で有効です。学内外のセミナーやカンファレンスに参加し、研究の最前線に触れることも、視野を広げるうえで役立ちます。
また、専門分野の教員や研究者と積極的にコミュニケーションを取るのもよいでしょう。教員や研究者から自らの知識やキャリアプランのフィードバックを受けることで、自らに必要な学習を明らかにできます。
大学教員に必要な資質
最後に大学教員になるために必要な資質を紹介します。
- 学問や研究への探究心
- 高いコミュニケーション能力
- 論理的思考力
学問や研究への探究心
大学教員になるためには、自らの専門分野に対する深い探究心が不可欠です。単に知識を蓄積するだけでなく、知識や研究によって世の中に貢献することに常に意欲的であることが求められます。
また、研究では長期間にわたり成果が目に見えて現れないことも少なくありません。それでもなお、目標に向かって粘り強く研究を続けられる忍耐強さも要求されます。
日々の研究活動において柔軟に新しい知識を取り入れ、アイデアやアプローチを模索し続けることが重要です。
高いコミュニケーション能力
大学教員にとって高いコミュニケーション能力は重要なスキルです。授業でのわかりやすい説明、学生とのディスカッション、他の教員や研究者との関係構築など、教員の仕事は人との接点に溢れています。自らの考えを明確に伝え、かつ他者の意見を理解し取り入れる能力が求められます。
教員は学生に知識を伝えるだけではなく、学生の研究やキャリアを形成する上でのメンターとしての役割も果たします。学生一人ひとりの才能を引き出し、それぞれに合った指導を行うには高いコミュニケーション能力が必要です。
さらに、学会でのプレゼンテーションや、他の教員との共同研究、大学運営における意思決定に至るなど、大学教員の役割は多岐にわたります。
このように、大学教員にはさまざまな場面でコミュニケーション能力が求められます。
論理的思考力
研究を進める上では、論理的思考力が求められます。
論理的思考力とは物事を理論的に考える力のことです。適切な手法で実験や調査を実施し、その結果をもとに論文を執筆するためには必要不可欠な能力です。
また、論理的思考力は学生への指導においても求められます。学生が論理的な考え方を身につけるためには、教員がまず論理的に学問を理解したり、アウトプットすることが欠かせません。
まとめ:大学教授になるには研究への熱意が欠かせない
大学教授になるには修士・博士課程から准教授までさまざまなプロセスを経る必要があります。また、研究で成果を上げるために忍耐強さや探究心、高いコミュニケーション能力などが重要になります。
まずは自らが熱意を持って取り組める研究分野を見つけることからはじめましょう。学部時代からさまざまな分野に触れて、教員と積極的にコミュニケーションを取りましょう。