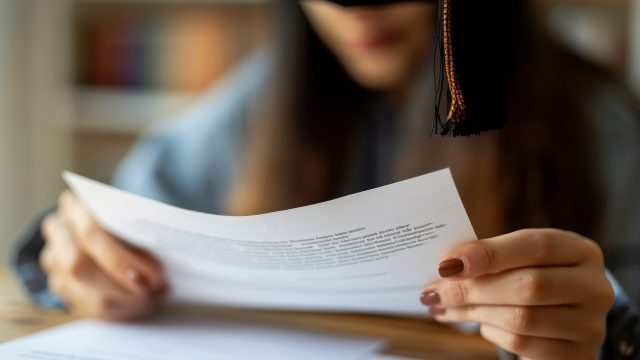大学(学部)入試では偏差値をもとに志望校を決めることも多いため、大学院進学を考える際も偏差値を参考にしたいと考える方がいるでしょう。しかし、大学院受験には偏差値は存在せず、別の観点から自分に合う大学院を選ぶ必要があります。
本記事では、大学院受験に偏差値がない理由やGPAとの関係について説明します。また、後半では自分に合った大学院の選び方や受験に向けた準備について紹介しているため、大学院進学を検討している方はぜひ参考にしてください。
大学院入試に偏差値はない
大学院入試には、大学(学部)入試でよく使われる偏差値のような指標がありません。大学入試の偏差値は、予備校が全国模試の結果を基に算出した数です。
志願者数が多く、試験科目もある程度共通する大学入試に対し、大学院や研究科によって試験科目や試験内容が大きく異なる大学院入試では、全国規模の模試が実施されていません。そのため、偏差値という基準にあまり意味がなく、そもそも偏差値を算出すること自体も難しくなっています。
そのため、大学受験のように「偏差値を目安に志望校を選ぶ」といった方法は取れません。大学院入試における志願先を決める際は、自身が大学院進学後に取り組みたい研究テーマを明確にして、その分野を指導できる教員がいる大学院を選ぶこととなります。また、大学院によって研究環境やカリキュラムが異なるため、自身が希望する研究内容に合う大学院を探すことも重要です。
大学院入試では、研究計画書の内容や筆答(筆記)試験・口述(面接)試験の結果などを総合的に考慮して合否が判断されるため、研究に対する意欲も重要な評価基準となります。
難易度は合格率から推測できる
大学院の難易度を知るためのひとつの目安として、合格率があります。合格率は受験者数に対する合格者数の割合を表すもので、一般的に合格率が低いほど入試の難易度(一概に試験内容のレベルを指すのではなく、入試に合格することの難易度)が高いとされています。多くの大学院では公式サイトで過去の合格実績を公開しているため、志望する研究科や専攻の合格率を調べることで、おおよその難易度を把握できます。
ただし、合格率は年度や入試方式によって変動することがあり、また同じ合格率であっても、大学院によって求められる専門知識のレベルは異なります。そのため、合格率はあくまで参考程度にとどめ、研究内容や指導教員との相性を重視して志望校を選びましょう。
また、大学院の場合は、定員と合格者数の関係にも注意が必要です。学部では、定員に近い人数を合格させること一般的ですが、大学院の場合は、定員は設けられているものの、大学院進学にふさわしい能力があるかどうかが審査されることが多いです。
そのため、志願者が定員を上回っている場合でも、定員より少ない人数しか合格者がいない場合もあります。大学院進学に向けては、自身の知識や研究計画が入学者としてふさわしい水準になるよう、準備を進めましょう。
大学院受験とGPAとの関係
大学院受験では、入試方式によっては学部時代のGPA(Grade Point Average)は重要な要素となります。GPAとは、履修した科目の成績を数値化して平均を算出したもので、学業成績を総合的に評価する指標として使われています。
多くの大学院の推薦入試(特別選考入試)では、一定以上のGPAを出願条件としています。一般的な目安として、3.0以上のGPAが望ましいとされていますが、基準は大学院によって異なるのはもちろん、学問分野や推薦入試の種類によって異なります。2.8~3.3程度のGPAを求められる場合が多いですが、中には、3.3以上のGPAを求められることもあります。
GPAを高めるためには、日々の授業への真摯な取り組みが不可欠です。予習・復習を欠かさず行い、定期試験や課題提出に向けて計画的に準備することで、着実に成績を積み重ねていけます。
一方、スタンダードな入試方式である一般入試の場合には、出願要件としてGPAの基準を設けているケースは少なく、学部時代のGPAによらず出願できることがほとんどです。
自身が希望する入試方式でGPAの基準が設けられているかについては、進学先を検討する早い段階で確認しておきましょう。
なお、入試方法別のGPAの重要性や、GPAの高め方についてより詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしてください。
自分に合った大学院の選び方
前述したように、大学院は偏差値で選ぶものではありません。大学院は専門的な研究を行う場所であり、進学後は2年以上の期間を費やすことになります。自分に合っていない大学院を選んでしまった場合、研究のモチベーションが下がり、研究を続けられなくなるリスクがあります。
そこで、自分に合った大学院を選ぶ際は、以下のポイントを理解したうえで選びましょう。
- 何を研究できるかを調べておく
- 指導を受ける教員を確認する
- 学費を調べておく
- 入試方式を調べておく
大学院のカリキュラムによって研究できる内容も異なります。そのため、自分の研究テーマや希望進路に合った環境を見つけることが何より重要です。まずは各大学院の研究分野や実績を調べ、指導を受けたい教員の専門分野や研究内容が自分の興味と合致しているかを確認します。
また、実務的な面として学費や入試方式(出願資格や出願書類)も重要です。修了までに総額いくら必要になるのか、自分に受験資格があるかどうかなどを確認しましょう。
より詳しく選び方について知りたい場合には、以下の記事を参考にしてください。
大学院受験に向けた準備

大学院への進学を目指す場合、研究計画書などの書類提出、筆答(筆記)試験、口述(面接)試験という複数のステップを経る必要があります。合格するためには、十分な準備期間を確保し、計画的に対策を進めていくことが重要です。
ここでは、大学院受験に向けてどのような準備が必要なのか、具体的に説明していきます。
研究計画書を作成する
研究計画書は、大学院でどのようなことを研究したいのか、その研究をどのように進めていくのかなどを具体的に記した書類です。入学後の研究活動の指針となるだけでなく、受験生の研究に対する姿勢や能力を評価する重要な材料となります。
研究計画書の主な項目は、次の通りです。
- 研究テーマ
- 研究テーマの背景・目的
- 先行研究
- 研究の内容
- 研究の方法
- 期待できる効果
- 参考文献
研究計画書を作成する際は、自身が研究したいテーマに関連する先行研究をしっかりと確認し、その上で自分の研究の独自性を明確に示す必要があります。自身の研究したい内容がすべて先行研究で行われている場合、研究の意義を明確に示せないからです。
また、研究の方法や期待される成果についても具体的に記述し、博士前期(修士)課程への進学の場合は、2年間という限られた期間で実現可能な計画を作成しましょう。
以下の記事では、より詳しく研究計画書の作成方法について解説しています。
大学院進学に必要な研究計画書に記載すべき項目とポイントを解説
筆記試験の対策を行う
筆記試験の科目は、入試方式によって異なります。しかし、専門分野の科目と外国語の試験が課されることが一般的です。
専門科目の試験では、学部レベルの基礎的な知識を体系的に理解していることが求められます。試験は主に論述式で実施されるため、論理的な文章を作成する練習を重ねましょう。
外国語試験では、研究に必要な語学力が問われます。大学院入試における外国語試験では、専門分野の文献を読解する能力が重視されるため、外国語で書かれた学術論文や専門書に慣れておく必要があります。試験では和訳や要約を課されることが多く、普段から外国語の学術文献に触れる機会を作りましょう。
専攻する分野によっては、英語以外の外国語を受験することもあります。事前に、自身の出願先で実施している外国語試験の科目を確認しておきましょう。
面接対策を行う
面接試験では、提出した研究計画書の内容や筆記試験の解答内容などについて質問されます。一般的に30分程度の時間で行われ、複数の教員が面接官となって評価を行うことが多いです。
面接官が重視するポイントは、主に以下の3つです。
- 進学への熱意があるか
- 研究に必要な論理的思考力を備えているか
- 指導教授とマッチしているか
面接では、単に研究計画の内容だけを確認されるわけではありません。研究に取り組む熱意や意欲、質問に対して論理的に答える能力があるかどうかも確認されます。
また、指導希望教員との研究テーマのミスマッチは、入学後の研究活動に大きな支障をきたす可能性があるため、面接では注意して確認されます。事前に指導を希望する教員の研究内容をよく理解しておき、自身の研究内容について指導希望教員の専門分野との関連性を明確に説明できるようにしておきましょう。
大学院入試の面接で聞かれる質問は?評価されるポイントや事前対策を徹底解説
まとめ:大学院受験では偏差値よりも研究環境やカリキュラム、指導希望教員が重要
大学院受験では、大学受験のような偏差値による難易度の指標は存在しません。そのため、大学院を選ぶ際は、研究環境やカリキュラムの内容、指導を受けたい教員の専門性、学費や入試方式などを総合的に検討することが大切です。特に指導教員との研究テーマの相性は、入学後の研究活動を左右する重要な要素となります。
大学院受験に向けては、研究計画書の作成や、筆記試験・面接試験の対策など、さまざまな準備が必要です。早めに情報収集を始め、十分な準備期間を確保することで、希望する大学院への合格に近づきます。
進学後の充実した研究生活のためにも、まずは自分の研究テーマを明確にし、それに合った環境を提供してくれる大学院を探しましょう。
中央大学大学院の資料請求はこちら