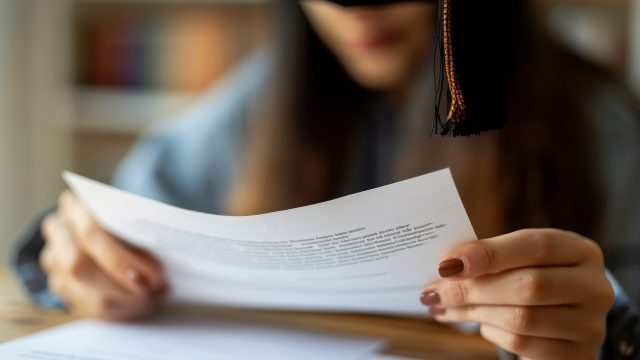大学院を受験する際には、多くの場合、研究計画書の提出が必要です。ただ、研究計画書は大学(学部)受験では求められない書類のため、なぜ作成する必要があるのか、どのような構成にすべきかなど、悩む方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、研究計画書の書き方を6つの項目ごとに解説します。高い質に仕上げるコツや文字数の目安、よくある質問まで詳しくまとめました。大学院入試に向けて「質の高い研究計画書を作成したい」という方は、ぜひ参考にしてください。
大学院入試で研究計画書が求められる理由
研究計画書は、大学院進学後に取り組む研究のテーマや方法などをまとめた文書です。大学院では自ら課題を設定し、主体的に研究に取り組む力が求められます。そのため、大学院入試においては、その能力を測る材料とするため、多くの大学院が入試の出願書類として研究計画書の提出を求めています。研究計画書を通じて、受験者の研究への理解度や計画性、研究者としての資質を見極めることが目的です。
また、大学院入試の面接(口述試験)では、研究計画書をもとに質疑が行われるケースが一般的です。研究の内容や進学(=研究活動を行うこと)に対する熱意をわかりやすく伝え、円滑なコミュニケーションを取るためにも、研究計画書はしっかりと作り込みましょう。次の章からは、研究計画書の書き方について解説していきます。
研究計画書の書き方|主な項目と注意点
研究計画書には主に以下の6項目を記載します。教員に研究内容がわかりやすく伝わるようにするためです。
この項目では、各項目ごとの注意点を解説します。
| 順番 | 項目 | 内容 |
| 1 | 研究テーマ | 研究のタイトルやテーマの設定 |
| 2 | 研究の背景・目的 | なぜその研究を行うのか、先行研究、研究の意義 |
| 3 | 研究内容 | 何を明らかにしたいのか、仮説や焦点 |
| 4 | 研究方法 | データの集め方や分析方法など |
| 5 | 期待される効果 | 研究の成果がもたらす社会的・学術的意義 |
| 6 | 参考文献 | 根拠となる書籍・論文の明示 |
ここからは注意点も交えながら説明しているため、研究計画書の作成に役立つはずです。
1.研究テーマ
まず、一文で簡潔に研究内容がわかるタイトルを設定します。長い文では研究内容を把握しにくいため、「〇〇における△△の研究」のように研究内容を一言で説明するといいでしょう。
ただ、研究内容によっては一言で説明するのが難しい場合があるかもしれません。その場合は無理に一言でまとめる必要はなく、「〇〇における△△の研究 ~◇◇について~」のようにサブタイトルをつけるのも良いでしょう。
【ポイント】
- 一文で簡潔に研究内容がわかるタイトルを設定
- 「〇〇における△△の研究~◇◇について~」のようにサブタイトルを付けるのも有効
2.研究の背景や目的
なぜこの研究を行うのかを明確にします。研究計画書を書く際には、その研究を行うに至った背景や目的の記載も欠かせません。それらを書くことで、自身の研究にどのような意義があるかをハッキリさせられます。
実際に書く際は、なぜこの研究を行うのか、その理由を簡潔にまとめるのがよいでしょう。なお、研究の背景や目的を説明する際には論文や専門書を引用するなどして、根拠や妥当性を示すことが重要です。これまでに行われた研究(先行研究)によって明らかになった成果を踏まえた研究計画でないと、当該分野への理解が不十分であるとみなされることにつながります。研究計画書の作成においては、自身が希望する研究計画を記載するだけでなく、先行研究を踏まえることが求められます。
そのため、日頃から専門書などを読み、自身の研究に関連する知識を深めておくことが大切です。また、研究内容が社会的にどのような意義があるかを説明するため、研究をするに至った社会的背景に触れるようにもしておきましょう。
【ポイント】
- 「なぜこの研究を行うのか?」を明確に
- 先行研究や専門書の引用で根拠を示す
- 社会的背景や課題意識も簡潔に触れる
3.研究の内容
研究計画書のメインとなる項目は、「研究の内容」です。この項目では、「研究を通して何を明らかにできるか?」を説明する必要があります。
研究のテーマや背景が明確だとしても、研究内容があいまいでは読み手に理解してもらえないかもしれません。自身の研究内容を伝える重要な部分になるため、できるだけ詳細かつ簡潔にまとめることが大切です。
【ポイント】
- 「研究で何を明らかにしたいのか?」を具体的に
- 重要な仮説や焦点をわかりやすく提示
4.研究の方法
研究方法を記載することによって、得られる効果が適切な方法で収集されたことを示します。実際に書く場合には、何を対象に研究を行い、どのような方法でデータを収集・分析するのかを記載するようにしましょう。大学院での研究(論文執筆)は限られた年数で行うため、実現可能な研究方法であるかどうかも重要なポイントです。調査対象となる文献や人、場所等にアクセスできるかを考えて、研究方法を決めるとよいでしょう。
【ポイント】
- 対象・手法・分析方法を明確に
- データ収集の手順、分析方法を簡潔にまとめる
5.期待される効果
研究計画書では、自身の研究を通してどのような効果が期待されるかも記述する必要があります。
期待される効果を書くことで、その成果によって社会にどのような影響をもたらすのかを把握しやすくなるためです。特に社会人の場合は、何かしら社会的な問題意識をもって受験を決めている場合もあるため、その問題を解決できるということも記述するとよいでしょう。
【ポイント】
- 研究がもたらす成果・学術的意義を示す
- 社会人受験生の場合は社会課題の解決にどうつながるかも明記
6.参考文献
最後に、進学を予定している研究分野の形式に合わせて、研究計画書を作成する際に参考にした論文や専門書を書きます。一般的には、少なくとも2〜3冊程度の参考文献を明記しておくことが望ましいとされています。参考文献が1本のみ、または記載がない場合は、研究の根拠や準備が不十分と見なされる可能性があります。
なお、参考文献の記載漏れがあれば、研究の根拠となる理論やデータの妥当性が失われてしまうため、必ず記載することが求められます。
【ポイント】
- 2〜3本以上の文献を明示
- 引用漏れは剽窃扱いになる恐れがあるため、提出前に必ずチェック
参考文献の記載漏れは“剽窃”と見なされるリスクも
参考文献の明示がないと剽窃(ひょうせつ)として疑われてしまう恐れがあります。そのようなことを防ぐためにも、使用した参考文献はすべて記載し、提出前に、漏れがないかをチェックするのが望ましいです。
剽窃とは、広辞苑によると「他人の詩歌・文章などの文句または説をぬすみ取って、人文のものとして発表すること」とあり、他人の著作から部分的に文章や語句などを盗み、制作物の中に自分のものとして用いることを指します。基本的に著作者名を明記しないまま勝手に使う行為すべてが剽窃に該当します。

研究計画書の文字数の目安
研究計画書の文字数や枚数は、一般的にはA4用紙1~2枚程度とされています。ただし、「○○字以内」や「○○字程度」といった具体的な指示があるケースも多いため、志望先の募集要項を事前にしっかり確認することが重要です。
【指定がある場合の注意点】
- 「○○字以内」と指定されている場合は、その文字数を超えないように作成しましょう
- 「○○字程度」と指定されている場合は、前後10%程度の文字数になるように作成しましょう
質の高い研究計画書を書くための4つのポイント

研究計画書は、ただ決まった項目を埋めればよいというものではありません。上記では研究計画書に必要な項目を紹介しましたが、実際に書く際には複数のポイントがあります。質の高い研究計画書を書くために、以下の4つのポイントを踏まえて取り組みましょう。
- 先行研究を踏まえ研究意義を明確にする
- 専門外の人にも伝わる書き方を意識する
- 根拠を示して論理的に展開する
- 独自性を出し、他の研究との差別化を意識する
これらのポイントを押さえることで、読み手に伝わりやすく評価されやすい計画書に仕上がります。
ポイント1.先行研究を踏まえ研究意義を明確にする
研究の新しさや意義を伝えるには、先行研究との違いや発展性を明確にすることが重要です。多くの場合、大学院で取り組むテーマは既存の研究の延長上にあります。そのため、研究計画書を作成する際は、まず今までの研究結果を踏まえ、自身の研究内容がどのように”+α”の視点を提供できるか、見極める必要があります。もし先行研究と大きく重複する場合には、テーマ設定自体を見直すことが求められます。
ポイント2.専門外の人にも伝わる書き方を意識する
審査する教員が必ずしも研究分野の専門家とは限らないため、誰が読んでも理解できる文章を意識しましょう。
内容を簡潔にまとめ、専門用語には丁寧な説明を添えることが重要です。特に第三者、できれば研究に詳しくない人に一度読んでもらうと、表現の分かりにくさや論理の飛躍に気づきやすくなります。研究内容の妥当性について不安がある場合は、指導教員や研究経験者に相談するのも有効です。
ポイント3.根拠を示して論理的に展開する
研究計画書の信頼性を高めるには、明確な根拠と論理的な構成が必要不可欠です。自分の主張を裏づける先行研究や理論、データなどを示しながら、読み手が納得できるよう論理的に展開しましょう。
あいまいな記述や推測だけでは説得力が欠けてしまうため、客観的な根拠に基づいた文章を心がけることが重要です。
ポイント4.独自性を出し、他の研究との差別化を意識する
他の研究との差別化を意識して自身の研究テーマにどんな独自性があるかを明確に示しましょう。先行研究との違いや研究を行う目的などを明確にすることで、自身の研究の意義を示すことができます。
独自性を考える上では、先行研究を基に論点が何なのか考えてみましょう。先行研究の見解について批判できる部分や修正できる部分を見つけ、そこに焦点を当てることで独自性のある研究となります。研究の意義が伝わりやすく、評価にもつながりやすくなります。
研究計画書に関するよくある質問
ここでは、研究計画書についてよく寄せられる質問を紹介します。
Q.大学院入試で研究計画書の提出が求められるのはなぜ?
A.研究計画書を通じて、受験者の研究への理解度や計画性、研究者としての資質を見極めるために、提出が求められています。
Q.大学院入試で提出する研究計画書には何を書けばよい?
A.研究計画書には主に以下の項目を記載します。
- 研究テーマ
- 研究の背景や目的
- 研究の内容と焦点
- 研究方法
- 期待される効果
- 参考文献
Q.大学院入試で提出する研究計画書の文字数は?
A.大学院によって指定が異なりますが、A4用紙1~2枚程度に仕上げることが一般的です。もし「○○字以内」または「○○字程度」と指定されている場合は、形式不備と判断されないためにも、文字数の超過や極端な不足は避けましょう。

研究計画書は事前にしっかり準備しておこう
研究計画書は教員に自身の研究内容を分かりやすく示すために必要な書類です。大学院入試の合否にも大きく関わるため、時間をかけて取り組むことが大切です。この記事の内容を踏まえて質の高い研究計画書を作りましょう。