自身の研究内容をさらに深めたい、あるいは専門性を高めてキャリアに活かしたいと考える人にとって、大学院への進学は有力な選択肢のひとつです。しかし、周囲が就職活動を始める中で、「いつまでに決断すればよいのか」「進学と就職のどちらを選べば後悔しないのか」といった迷いや不安を抱く方も少なくありません。
本記事では、大学院進学を検討している方に向けて、多くの学生が進学を決める時期や、文系・理系の違い、時期別のメリット・デメリット、そして後悔しないための判断軸についても解説します。
大学院進学はいつ決めるべき?
大学院進学を決める時期は学部3年生が最多ですが、文系(人文・社会科学系)では4年生以降に決めるケースも珍しくありません。
大学院の入試は、入試方式によっては夏季(4月~7月)に実施されることもありますが、秋季(8~11月頃)と春季(1~3月頃)に行われるのが一般的です。実際、学生たちはどの時期に進学を決断しているのか、文部科学省の調査結果をもとに、傾向を確認してみましょう。
学年別の傾向|文科省調査でわかる進学決断の時期
文部科学省 科学技術・学術政策研究所が実施した「修士課程(6 年制学科を含む)在籍者を起点とした追跡調査(2021 年度修了(卒業)者及び修了(卒業)予定者に関する報告)」によると、修士(博士前期)課程進学を決めた人のうち、31.4%が学部3年生の時に大学院への進学を決断しています。
学問分野ごとの割合をまとめると、次の通りです。
- 学部3年生で決断:31.4%(最多)
- 学部4年生で決断:22.8%
- 大学卒業後に決断:17.0%
【文系は4年生以降でも多い】
- 人文学系:学部4年生が32.7%
- 社会科学系:大学卒業後が40.7%
【理系は3年生までが主流】
- 工学系:学部3年生で40.0%
- 理学系:学部3年生で38.9%
| 院進学を決めた時期 | 学部入学前 | 学部1年生 | 学部2年生 | 学部3年生 | 学部4年生 | 大学卒業後 |
| 全体 | 16.5% | 4.8% | 6.0% | 31.4% | 22.8% | 17.0% |
| 理学 | 24.6% | 6.4% | 6.3% | 37.9% | 21.4% | 2.9% |
| 工学 | 22.3% | 7.0% | 6.8% | 40.0% | 20.5% | 2.7% |
| 農学 | 20.4% | 4.0% | 5.7% | 38.9% | 27.3% | 3.5% |
| 保健 | 17.4% | 4.0% | 5.6% | 20.4% | 16.8% | 32.3% |
| 人文 | 8.1% | 3.4% | 7.8% | 29.0% | 32.7% | 17.8% |
| 社会 | 5.0% | 2.1% | 5.1% | 21.7% | 23.6% | 40.7% |
| その他 | 10.0% | 2.6% | 5.0% | 24.7% | 31.0% | 24.6% |
参考:文部科学省 科学技術・学術政策研究所 第 1 調査研究グループ|修士課程(6 年制学科を含む)在籍者を起点とした追跡調査(2021 年度修了(卒業)者及び修了(卒業)予定者に関する報告)
理系のほうが文系よりも早く決断する傾向にある理由
文部科学省の調査結果では、工学・理学といった理系では、学部3年生で決断する割合が40%前後と最も高くなっています。メーカーの開発職や研究職など専門性の高い職業では、修士課程修了(修士号の取得)がキャリアの前提となっていることが多く、文系に比べて大学院進学を早く決断する傾向があります。
一方、人文・社会科学系などの文系では、学部4年生以降や大学卒業後に決断する割合が30〜40%と高めです。就職活動を経験したあとに探求したいテーマを見つけたり、社会に出てから「より専門性を高めたい」と感じて進学を選んだりするケースが多く、その分、決断の時期が後になる傾向があります。
大学院進学を早め・遅めに決断するメリット・デメリット
大学院進学は、早めに決断すれば入試準備や研究室選びに余裕が持てる一方、遅めに決断すれば就職活動との比較や卒論の執筆を通じて納得感と目的意識を高められます。
つまり、院進をいつ決めるかに正解はなく、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自分の状況やキャリアに合ったタイミングを選ぶことが重要です。
どちらの選択にもメリットとデメリットがあり、自分に合ったタイミングを見極めることが重要です。以下に、早め(学部1〜2年次)に決断する場合と、遅め(学部4年次以降)に決断する場合のメリット・デメリットをまとめました。
| メリット | デメリット | |
| 早めに決断 | ・入試対策や研究計画の準備に十分な時間をかけられる
・大学院、研究室、指導教員をじっくり検討できる ・希望する指導教員との関係構築を早期に始められる |
・就職など他の選択肢を十分に検討しにくい
・学部高学年で興味関心が変わり、後悔する可能性がある ・研究テーマが固まらず、具体的な計画を立てにくい |
| 遅めに決断 | ・就職活動と比較検討し、納得感を持って選択できる
・卒論を経て大学院で学ぶ目的意識が明確になり、研究の質が高まる ・自身の適性を見極められる |
・研究計画を立てる時間が限られ、指導教員や研究室の検討時間が少ない
・入試対策や書類準備の時間が限られる ・周囲に進路決定者が増える中で、焦りや孤独感を感じやすい |
大学院進学を遅めに決断するメリット
「周りはもう進路を決めているのに、今からで本当に間に合うのだろうか」と不安に感じる人もいるかもしれません。しかし、学部4年生以降にじっくり考えてから決断することには、以下のようなメリットがあります。
就職活動と比較し、納得した進路を選べる
学部3年生の段階では、社会で働くイメージがまだ漠然としている人が多いでしょう。しかし、実際に就職活動を経験し、企業や官公庁のインターンシップに参加したり、社会で働く先輩の話を聞いたりすることで、社会人の解像度は一気に高まります。
「企業や官公庁で働くとはどういうことか」「自分はどんな働き方や生き方をしたいのか」を具体的に知った上で、「学部の学びよりも高い専門性を身につけたい」「自分は研究の道に進みたい」と決断したのであれば、それは学部卒での就職という選択肢も含めて真剣に比較したうえでの前向きな選択といえるでしょう。
【文系の場合】
就職活動を経験してから大学院進学を選ぶケースも多く、社会での働き方と研究の両方を比較し、やはり研究を深めたいと思えたときの納得感は大きいです。
【理系の場合】
就職活動と研究職のキャリアパスを比較できるため、修士号が必要な職種に進むか、学部卒で就職するか、現実的に判断できます。
このように納得感を持って選んだ進路だからこそ、進学後の研究にも高いモチベーションで取り組めるはずです。
目的意識が明確になり、研究テーマの質が高まる
進学を遅めに決断する大きなメリットは、大学院での研究目的がより明確になり、テーマの質を高められることです。
その背景にあるのが、学部4年生で取り組む卒業論文です。卒業論文は多くの学生にとって初めての本格的な研究経験であり、先行研究を読み込み、データを分析し、指導教員と議論を重ねる中で、「この分野は本当に面白い」「さらに深く探究したい課題がある」と感じる瞬間があるでしょう。
【文系の場合】
卒業論文の執筆を通じて、さらに深く探求したいテーマが見つかったり、社会の課題をどう研究で解決できるかを考えるきっかけが得られたりすることで、修士(博士前期)課程で取り組むテーマを明確化させやすいです。
【理系の場合】
研究室での実験やプロジェクト経験を経て、自分はこの領域に適性があると自覚できます。テーマを深めるだけでなく、研究手法の選択肢も具体的に描けます。
こうした体験を通じて、学部3年生の時点では漠然としていた興味関心が「なぜこの研究が必要なのか」「修士課程の2年間で何を明らかにしたいのか」といった具体的な目的意識へと発展します。その結果、研究計画書の説得力が増し、口述試験(面接)でも自信を持って受け答えできるようになるのです。
自分の適性を深く見極め、後悔のない選択ができる
大学院での研究活動に必要なのは、必ずしも授業の成績だけではありません。問いを掘り下げ続ける探究心や、筋道を立てて考える論理性、すぐに成果が出なくても諦めない粘り強さが求められます。
【文系の場合】
ゼミでの活動や卒業論文を通して、研究自体が楽しいかどうかを見極められます。研究が自分に合っていれば進学を選び、合っていなければ就職にシフトできます。
【理系の場合】
実験や研究室での活動が日常になるため、そうした環境を心から楽しめるかが適性の判断基準となります。学部後半の経験を経て適性を確認できるのは大きな利点です。
学部でのゼミ活動や卒業論文を執筆する過程は、自分に研究者としての適性があるかを確認する絶好の機会です。卒業論文の研究を心から楽しめているなら、大学院でも充実した研究生活を送れる可能性は高いでしょう。反対に、苦痛に感じることが多ければ、別の進路を考える判断材料にもなります。
このように、自分の適性を見極めてから進学を決められることは、結果的に入学後に後悔しにくいという安心感につながります。
大学院進学を遅めに決断するデメリット
大学院進学を遅めに決断することには多くのメリットがある一方、いくつかのデメリットも存在します。
指導教授・研究室選びに影響が出る可能性がある
人気の高い研究室や指導教員のもとには、学部3年生の段階から連絡を取る学生もいます。出願時期が始まっていなくても、教員が早めに相談に来た学生を把握しており、研究への熱意や適性を知る機会が多いほど有利に働くことがあります。
【文系の場合】
進学の決定が遅れると、研究テーマが明確になる時期が遅くなり、希望の指導教員への事前連絡も出願期間直前となる可能性があります。事前の相談に十分な時間が取れず、自身が希望する研究テーマと合う指導教員を見つけられない場合もあります。
【理系の場合】
実験設備や指導可能人数が限られるため、配属が物理的に難しくなるリスクがより高いです。
そのため、学部4年生の後半になってから初めて希望を伝えると、他の志望者との比較で不利になる可能性があります。こうした状況を避けるためにも、進学を少しでも考えているなら、できるだけ早く研究室の説明会に参加したり、公式サイトを確認したりと、早めに情報収集を始めておくことが大切です。
試験対策や研究計画書の準備が不十分になることがある
大学院入試の準備は、卒業論文の執筆や卒業研究という、多くの学生にとってもっとも忙しい時期と重なります。卒業論文の追い込みと並行して、専門科目の筆答試験対策や、TOEIC®やTOEFL®といった英語のスコアの提出準備、研究計画書の作成を行う必要があります。
【文系の場合】
出願期間や試験日までの機関が短く、筆答試験や英語のスコア提出に向けた準備時間が少なくなります。また、研究計画書の作成に充てられる時間も限られるため、内容を精査し、質を高めるのが大変です。
【理系の場合】
卒業研究の実験・解析と並行して専門科目の試験勉強をする必要があり、体力的にもハードになりがちです。また、早期に大学院進学を決める学生が多い中で、卒業研究と大学院進学後の研究の着手の両方が中途半端になってしまう懸念もあります。
特に研究計画書は、関連分野の先行研究の論文を読み込み、自分の研究の新規性や意義を論理的に示す必要があるため、入試の4〜6か月前に作成に取りかかることがおすすめです。準備が不十分なまま提出した書類は、短時間で仕上げたものであることがすぐにわかってしまいます。決断したら試験日から逆算して具体的な学習計画を立て、徹底してスケジュールを管理することが不可欠です。

周りの進路決定が精神的な負担になる
友人たちが次々と内定を得て就職活動を終えていく中で、自分だけが受験勉強を続ける状況は、精神的な負担が想像以上に大きいものです。「自分だけまだ進路が決まっていない」という焦りや孤独感を感じることもあるでしょう。
【文系の場合】
周囲の大多数が就職活動を終えて進路が決定しているため、孤立感が強まりやすいです。また、進路を大学院進学に絞って受験準備をしている場合は、卒業後の進路が決まらない不安もあるでしょう。
【理系の場合】
研究室の同期は進学前提で動いているケースが多く、その分すでに進学が決定している(大学院入試に合格している)ことも多いです。進路選択に対する孤独感は少ないですが、周囲より遅れていることに対する焦りを感じやすくなります。
このような時期を乗り越えるには、同じように大学院進学を目指す仲間や、親身に相談に乗ってくれる指導教員、一足先に同じ道を経験した先輩など、自分の状況を理解してくれる味方を見つけることが効果的です。一人で抱え込まず、進捗や悩みを共有できる存在がいるだけで、精神的な負担は軽減され、最後まで走り抜くためのモチベーションを保ちやすくなります。
大学院進学と就職で迷ったときの判断軸3つ
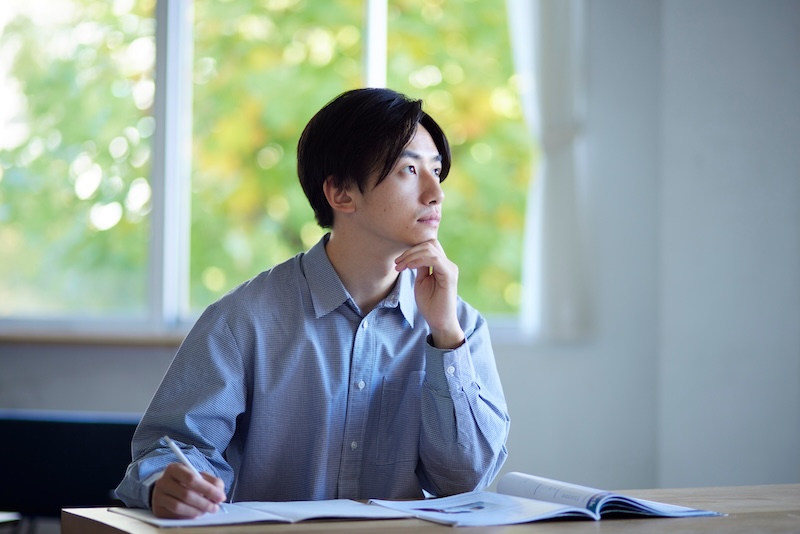 大学院への進学と就職で迷っているときは、以下の3つの問いを自分に投げかけてみてください。問いに対して「はい」と答えられるかどうかが、進学を選ぶべきかどうかを判断する基準となります。
大学院への進学と就職で迷っているときは、以下の3つの問いを自分に投げかけてみてください。問いに対して「はい」と答えられるかどうかが、進学を選ぶべきかどうかを判断する基準となります。
「なぜ学びたいか」という目的意識は明確か
大学院での研究は、決して楽ではありません。思うように成果が出なかったり、膨大な文献を読み込む大変さに直面したりすることもあります。「卒業論文で解き明かせなかった疑問を追究したい」「社会問題の解決に役立つ専門知識を身につけたい」といった、知的好奇心や明確な目的意識がない場合、途中で挫折してしまう可能性が高まります。
それを避けるためには、進学の動機を振り返ることが重要です。「就職活動から逃げたい」「まだ学生でいたい」といった消極的な理由ではないか、自分に問いかけてみてください。
修了後のキャリアパスを具体的に描けているか
大学院進学は、2年間以上の時間と200万円前後の学費を投じる、大きな自己投資です。その選択が将来どのような成果につながるのか、あらかじめ具体的にイメージしておくことが大切です。
そのためには、現実的な視点で情報を集めてみましょう。例えば、興味のある職種の求人票を確認し、応募条件に「修士課程修了以上(修士号取得)」と記載されているか、大学院で得られる専門性がキャリアアップにつながるのかを調べてみてください。
さらに、実際に大学院を修了した先輩に話を聞き、学びがどのように仕事に生かされているかを知るのも有効です。「研究職や専門職に就きたい」「研究者として歩みたい」などのゴールを設定し、その実現に大学院進学が本当に必要か、あるいは有利に働くのかを冷静に判断しましょう。
「みんなが行くから」という理由で決めていないか
決断を下すのは、あなた自身です。ただし、人は無意識のうちに周囲の環境や意見に影響を受けることがあります。例えば理系の研究室では「修士課程に進学するのが当たり前」という雰囲気があったり、家族や指導教員から将来を思って期待をかけられたりすることもあります。
周囲の意見は参考になりますが、大切なのはそれが自分の本心と一致しているかどうかです。「もし周りの全員が反対したとしても、自分はこの道を選びたいか?」という問いに自信を持って「はい」と答えられるなら、大学院に進学した後も前向きに研究を続けていけるでしょう。
大学院に進学するか就職するか、悩んでいるのなら、ぜひ以下の記事を参考にしてください。
大学院か就職か悩んだ場合はどうする?それぞれのメリット・デメリットを解説
大学院進学を決断したらすべきこと
大学院へ進学する意志が固まったら、合格に向けて計画的に準備を進める必要があります。やるべきことは多岐にわたりますが、次の3つのステップに沿って取り組めば、効率よく進められるでしょう。
1.研究室や指導教員の情報収集
指導教員・研究室選びは、大学院生活と大きく関わる重要な段階です。大学のウェブサイトなどで概要を確認し、指導を受けたい教員の名前で検索して、その教員が執筆した論文や書籍に目を通しましょう。 研究内容やスタイルが自分の関心と本当に合っているかを確かめられます。
候補が絞れたら、大学院の説明会に参加したり、指導教員にメールでアポイントを取って研究室を訪問したりしてみましょう。在籍している先輩の様子や研究室の雰囲気は、実際に足を運んでこそわかるものであり、その体験が進学後のギャップを防ぎます。
2.出願準備
志望先が決まったら、具体的な出願準備に入ります。まずは志望校のウェブサイトから募集要項をダウンロードし、印刷して隅々まで確認しましょう。 出願期間や試験日、必要書類を把握し、スケジュールに落とし込むことが大切です。
特に合否を大きく左右するのが研究計画書で、大学院で「何を」「なぜ」「どのように」研究したいのかを記載します。先行研究を十分に調べたうえで早めに草稿を作り、指導教員やゼミの先生に見てもらいながら何度も修正を重ねましょう。
3.入学試験対策
専門科目(筆答試験)や英語スコア対策、研究計画書を基にした口述試験(面接)練習を行います。専門科目の過去問がウェブサイトなどで取り寄せられる場合は、必ず入手しておきましょう。出題傾向や必要な知識レベルを把握することで、効率的な学習計画が立てられます。
口述試験では、提出した研究計画書をもとにプレゼンや質疑応答が行われます。「なぜこの研究をしたいのか」「2年間でどこまで明らかにできそうか」「大学院での研究をもとにどのようなキャリアを考えているか」といった問いに自信を持って答えられるよう、研究計画を誰かに説明する練習を繰り返しておきましょう。

大学院進学の決断時期に関するよくある質問
大学院進学を検討していると、「いつ決めるべきか」「遅くなったら不利なのか」など、多くの疑問が浮かんでくるものです。ここでは、大学院進学の決断時期についてよくある質問にお答えします。
Q. 大学院進学を決める時期は、学部3年生がベストですか?
A.学部3年生で決める人が最も多いのは事実ですが、それが唯一の正解ではありません。理系では修士課程がキャリアの前提となる場合が多いため早めに決断する傾向がありますが、文系では学部4年生になってからや就職活動を経験した後に進学を決めるケースも少なくありません。
Q. 進学の決断が遅れると不利になりますか?
A.指導教員や研究室選び、出願準備に割ける時間が限られる点では、不利になる可能性があります。ただし、遅く決めるからこそ、他の進路(就職)と比較して納得した上で決断できる、研究テーマの質が高くなるといったメリットもあります。
Q. 就職と大学院進学で迷ったときはどう判断すればよいですか?
目的意識や修了後のキャリアパス、そして周囲に流されていないかの3つを判断軸に考えるのがおすすめです。
最適な決断タイミングは人それぞれ!決断したらまず情報収集を

大学院進学を決める時期に、唯一の正解はありません。学部3年生で決める人が多いものの、文系と理系では傾向が異なり、最適なタイミングは一人ひとりの状況によって変わります。大切なのは、周囲に流されず、自分自身の目的や将来像と真剣に向き合うことです。
この記事で紹介した3つの判断軸を参考にすれば、進学を決める時期が多少遅くなっても、その分のメリットを活かせるはずです。ぜひ本記事の内容を参考に、自分にとって納得のいく進路を選んでください。






